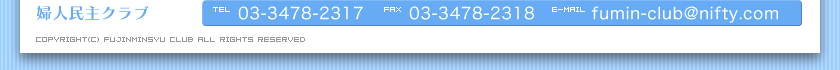第1259号
2008年2月10日(日曜日)発行
私の視点 澤地久枝
多喜二忌に
アンダンテ・カンタビレ聞く多喜二の忌
多喜二忌や麻布二の橋三の橋
二月二十日は、作家小林多喜二の命日である。昭和八(一九三三)年、地下生活中スパイに売られ、築地警察署の特高による拷問で、無残に殺された。二十九歳と四か月の若さだった。
右の俳句は、非合法生活の多喜二を助け、夫婦になった伊藤ふじ子が生前書きのこした未完の文章のなかにあった。
死に至らしめる特高の拷問など、信じない若ものも多いかも知れない。体験を語れる人はあいついで亡くなって、「特高警察政治」の時代は過去に埋没してしまいそうにみえる。
最高刑は死刑という治安維持法は、戦争が終わるまで生きていた。権力を背景にするなさけ容赦のない実行者が、特高とよばれた男たちである。
どんなにひどいテロがあったか、反戦・反権力の行動が(資金援助のシンパ活動をふくめて)文字通り命がけであった時代のことだ。
その血の色が世の中を染めつくしたとき、日本は大きな戦争へ突入した。
多喜二の死は、近づく時代への命を賭けた警告であった。多喜二の人生の壮絶さを思うとともに、彼を支えた伊藤ふじ子、その母き志、多喜二の青年期からの恋人田口タキ、彼の母と弟妹の「たたかい」を考えずにはいられない。あの時代、勇気をもって生きた人たちは、ずっと沈黙のなかにいた。
地下潜行中の小説『党生活者』は、『転換時代』とタイトルを変え、「小林多喜二/血の滲む絶作」のリードをつけて「中央公論」にのった。かなり目立つ新聞広告が出ている。
おなじく『転形期の人々』は雑誌「改造」に掲載された。
もとより、伏字や削除はある。
私が思うのは、地下の多喜二と連絡をとりあい、危険を覚悟の上で、作品を受けとる方策をこうじた雑誌記者の勇気である。体制迎合もしくはなにもしないのが安全と誰の目にもうつっていた社会で、あえて多喜二の側に立とうとした人たちがいたということの意味を考えたい。
現在の政治は悪いといっても、多喜二の時代のようではない。しかし私たちの抵抗が弱ければ、愚かで残忍な政治は何度でもくり返される。最後は一人ひとりの意志が問われよう。
多喜二忌は、追悼の日であるとともに、わが生き方を考える日でもある。(作家)