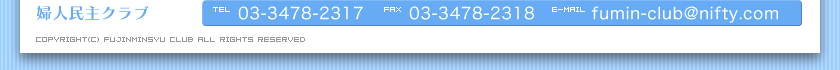第1192号
2006年1月30日(月曜日)発行
婦民と私
戦後の自分史に婦民を重ねて
都庁支部 加藤 富子さん

加藤さんが婦民に入会したのは、一九五八(昭和三十三)年に東京都庁に就職して数年後のことでした。都庁に婦民の支部をつくりたいと熱心に動いていた人がいて、その人に誘われました。だから、都庁支部発足当初からの会員です。
ところが異動で職場が本庁から主税局に変わり、都税事務所勤務となったために、しばらく婦民から離れることになります。再入会したのは、婦民が「再建」となってからのこと。帰ってきた加藤さんは次々に仲間を誘いました。今都庁支部を支える何人かは、その頃、加藤さんが誘った仲間たちです。
加藤さんは小学(当時国民学校)一年で敗戦を迎えました。お父さんは北区十条の駅前で八百屋を営んでいましたが、建物の強制疎開で埼玉県の武蔵嵐山へ。フィリピンでお父さんが戦死したことを知らされたのもこの地でした。加藤さんはここに小学五年生までとどまることになりました。
「母が大へんでしたね」。残された三人の娘(加藤さんは次女)を造花づくりで育てあげたお母さんは今、「九十三歳になりました」
「私は十五歳で働き始めましたから、結局五十年働き続けたことになりますね」と加藤さん。最初の職場は化粧品会社、働きながら夜間高校へ通いました。高校を卒業すると同時に都庁へ。全日制の卒業者との差別待遇がいやだったと加藤さんはその会社を辞めた理由を語りました。
結婚、そして共働きで二人の子どもを育てました。育児休暇も身近にゼロ歳児保育所もなかった当時、「二人の子どもは二歳まで実家の母にみてもらいました」。子どもに予防注射を受けさせに行く時間をと労働組合の婦人部で要求したのを覚えています。十三年前に夫君を亡くしました。子どもたちを独立させ、今は独りぐらしです。
加藤さんといえばカメラ。婦民新聞を飾る都庁支部関連の写真のほとんどは、加藤さんの撮影です。一番の目的は「山」を撮ること。今も山仲間のグループで時々、登山を楽しみます。さらに合唱団の団員であり、絵の腕前にも定評があります。都庁支部が婦民創立六十周年の記念日に向け、憲法を守り、日本を「戦争する国」にしないとの思いをこめ作成する絵はがきの四人の描き手の一人が加藤さんです。
私の保健室日記
「どうしたの?」(18)
「まゆこも成長したよ!」
まゆこ。中三生。面長に切れ長の目で美人顔。茶髪でメイクした顔はとても十五歳には見えない。昨秋から学校には来なかった。不幸なことに父と母はかなり前から別生活。小学校時代から父と母の間を行ったり来たり。兄と三つ歳下の弟もいる。
昨秋から母のもとに。通常の学校生活が送れないまゆこにとって母のもとから二時間かけて通学することは困難だった。母のもとでは〝職場体験〟をしていたとのこと。
年が明けて三学期のスタートは父のもとからと担任から聞いていた。ある日久しぶりに保健室に姿を見せた。五限目が始まってしばらくたっていた。
「さゆり!(生徒は私のことをこう呼ぶ)おにぎりを食べさせて!」ラップに包んだおにぎりを私の胸の前に突き出した。目は穏やかだった。食べ始めたまゆこに私は「おいしそうに食べてる!!自分でつくったの」とたずねた。「お母さん!」「えっ、いまお父さんのところじゃなかったの」「うち、いま最高、幸せ気分やねん。お母さんな、お父さんとこに来てんねん」「三月からみんな一緒に住むことになってんよ」「あっでも残念なことがひとつあるわ。さゆりに弟、会わされへんわ」――校区外に家を探しているという。
どんないきさつがあったのかわからないがとにかく壊(こわ)れていた家族が修復する!ひとつ屋根の下で揃って家族がまた生活をつくるという。私はまゆこの幸せ気分がずっと続くようにと心の中で祈った。
それから毎日一回は保健室に姿を現わす。こんな会話もあった。「さゆり、お母さん、きょうは長居に戻ってんねん」「えっ?」――もう戻ったの――心が騒いだ。「あんね、仕事すぐやめさせてもらわへんねんて。休んでばっかりできへんから。介護の仕事、長居の方は大変やねんて。ここら辺の老人は家族とかもいるけど、あっちの老人は一人ぽっちの人が多いねんて」「そおう。お母さんも苦労してはるんやね。でも、お母さんとそんな話をしてるんやね。いい関係じゃない、お母さんと。あなたからこんな話、聞けるなんて。先生嬉しいわ」「うん、まゆこも成長したよ」――私は胸があつくなった。
一年半前は母と激しく衝突してはリストカットをくり返していたまゆこだった。子どもたちの成長の可能性を信じて、受けとめ励まし続けることの大切さをかみしめようと思う。(大阪 中学養護教諭)